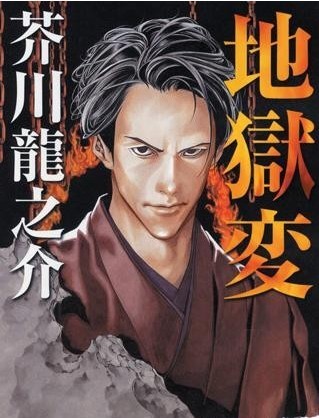�����(����)-��1����
�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������
��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���
�������ֻ����ʡ�m��
������
��q�Шr���q�Шr��ӭ���١�������������
���u�����������q�q��������������������
�������������t��������
�����������p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�桡Ȩ���顡ԭ��������
����������������������������������������duansh1204��������
�������������ݰ�Ȩ���������У�
������ˤΈ��ϡ�1
�����L�˴�����ʤ��顢�i���T�줿ͨѧ·��i�����@�λ��Ϥ��Ǥ�ɢ�äƤ��ޤ���ľ���ˤϾvɫ���~������ï�äƤ��롣��ѧ�ڤ�ʼ�ޤäƤ⤦2�L�g���U�ä����¤������饹�ˤʤ�����Ԥ���ꡢ���ޤ����ӳ���Τʤ����饹���䵨��ͨ��Խ���ƴ���Ƥ��ޤä���4�¤���ꡢů�����ݺ���С���ä����ĵؤ������ʤä��֥쥶������Ʒ����٤����һ���Ϥޤ�����Ƥ���ܥ����Ϣ�ष�������դ���ߚ��¤�23�Ȥ��Ȥ�����Ҋ������^���Ф��^���ä���
��������ˤϡ�˽���֥Όm�ߵ�ѧУ��ͨ����У2��������ƫ����Ϥ��¡����ݩ���Ĥˤ��������Ƥ����֥Όm��У�ϡ��ش����ƶȤ��뤷�Ƥ��ơ���ԇ�Εr��ѧ��10λ���ڤ���ä���ͽ�ϡ�ѧ�M����ͨ�M��������ѧУ���v����Τ�ȫ��ѧУ��ؓ���Ƥ���롣���δ���ꡢѧ�ڤ��Ȥˤ�����ĩ�ƥ��Ȥǡ�ѧ��10λ���ڤ�ʳ���z��Ǥ��ʤ��Ȥ����ˤ����Y��ϰ��Z����Ƥ��ޤ����Ĥޤꡢ��������B���äƤ���ζ���o�����Ԥ����Ȥ������˳ɿ��������ʤ��ȡ��ش��ƶȤ��ܤ��뤳�Ȥ������ʤ��ʤ롣
�����ˤϤ����ش��ƶȤ��ܤ��Ƥ���һ�ˤ��ä���1��ǰ�ޤ�ĸ�Ӽ�ͥ�ǡ��٤��Ǥ�ĸ��ؓ����p�餽���ȡ���ѧ�����ߡ����ʤ���������ش��ƶȤ��뤷�Ƥ����֥Όm��У�����Y����Ҋ�¤˺ϸ����٤��Ǥ�ĸ��S�ˤ����Ƥ����������Ԥ�һ�Ĥ��B���äƤ������ˤ��ä�������У����ѧ����ǰ������Ŭ����ˮ���ݤˤ���褦�ʳ����¤��𤳤ä���
�������ʤ�ĸ�����ٻ餷���Τ��ä���
���ٻ����֤ˤϡ����ˤ�ͬ������ӹ��������������ӹ��⡢ͬ���֥Όm��У��ͨ���趨���ȴΡ�������^���Ф���äƤ��ơ����ˤ�ãȻ�Ȥ��Ƥ��ޤä�������ԭ��ϡ��ޤ�����ˡ�ĸ���ٻ餹�����֤��������ȡ������ƴΤϡ��ٻ餹��ޤ�֪�餻�Ƥ���ʤ��ä����Ȥ���ͻȻ���Ф�Ҥ��B��Ƥ��ơ��ٻ餷�ޤ��ʤ����Ԥ���Ƥ⡢��ѧ����I���Ƹ�У���ˤʤ��ӹ�������˿ष������Ϥä����Ԥäơ��B���Ӥʤɡ��ɤ��Ǥ������Ƚ��ˤ�˼�äƤ�����
�����ˤ�ͬ������ӹ��ϡ��i���Ԥ����ݤ��������뤤�Ը�Ƥ�����ͻ������Ƥ��ޤä��x�ֵܤˡ����ˤϬF״�����դǤ��ʤ��ޤޡ���������������Ȱ��٤��Τ��ä���ĸ�H���ٻ餷���n�ĤϽ�Ǥ������줺�����ˤ��ؤ��Ф˂��Ȥ��ƲФäƤ��ޤä���
��һ�����m���Ƥ���ĸ�����ھw���Фȸ����ϤäƤ����Τ��������⡢�Y�餷�Ƥ���Έ��줿�Τ�����ޤ�ʹ�äƤ������֤����ꡢ�־A�����äƴ����ä��������ܤ�������ʤɤ��ʤ��顢״�r����դ����˷��ʤ���ĸ�H���ٻ餷���F�g���ܤ���줿�Τ��ä���
�����˩��������äȴ��äơ�
���������ךݤ����������ơ����ˤϤ���Ϣ���������귵�ä����h����Ҋ����Τϡ�ȥ���ֵܤˤʤä��i�ǡ����ˤ��ä��֤����ʤ����ߤäƤ��롣�۽ǡ�ͬ����У��ͨ�äƤ��������顢һ�w���Ф��ʤ������ĸ��ЦǤ����Ԥ����x���⤽�줬������Ц���ʤ����Ԥä��Τǡ����ˤ�һ�w���Ф�������ʤ��Τ˚i�ȵ�У���ʤ���Ф����ʤ��ʤä���
���i�Ϥ����ɤ��Ȥ�˼��ʤ��ä��褦�ǡ����ˤ�Цǡ��֤��ä����ȷ��¤������줬�o�Ԥ˿����������ˤ�һ�ˡ������݆���Ф����Ƥ��ʤ��ΤǤϤʤ��Τ��ȡ��r�ۡ������ˤʤ�Τ��ä���
�������W�̤��롹
�����ˤ���rӋ��Ҋ�Ĥ�ơ��r�̤�_�J���롣�ޤ��W�̤���褦�ʕr�g���ǤϤʤ������Τ��Ȥ�˼�������ȡ��i����Ƥн��ˤޤ��W�̤���Τ�Ŀ��Ҋ���Ƥ������Х��Х��ȥ�ӥ˽���Ƥ����i�ˡ��Ȥ��Ф��ȡ�С�������Ǹ椲�ơ����ˤϤ��������ȳ��Ƥ����Τ��ä���
���������𤳤��Ƥ����Ф褫�ä��Τˡ�
���ޤƤ�ä�֪��ʤ��ä����项
��Ц���ʤ���Ԓ�������Ƥ���i�ˡ����ˤ��ؚݤʤ��𤨤���1��U�ä���Ǥ⡢�i�Τ��Ȥ��T��ʤ���Ԫ������Ҋ֪����ä����Ԥ��Τ⤢��Τ����������ֵܤ��Ӥʤ��ä������ǡ��ֵܤ��Ԥ��ΤϤɤ��Ԥ���ΤʤΤ��֤���ʤ�������ˡ��i��ĸ�ȸ����������ä���������֪�äƤ������Ԥ����Y�餷���ᤫ��֪�餵�줿���ˤȱȤ٤�ȡ��Q���β�ϚsȻ�Ȥ��Ƥ��ơ����줬��Ӌ�˱ڤ����餻�Ƥ����Τ��ä���
�����ˤäư��β��ݤ˽~�����ʤ���͡���äƤ���Ф����Τˡ�
���ˤβ��ݤ˄��֤����Τϥޥʩ��ߡ����������H�����٤ˤ���x����ä��Ԥ����餤������
�������ޤ����������͡�
���٤������Ť���������������������ɡ����ˤϤ����oҕ���ƚi��ʼ��������Ǥ������٤��i����äƤ���������ѧУ���Ф��Τ��W���ʤäƤ��ޤä��Τ�������ʤȤ���������Ԓ�Ƥ���С���ä��W���ʤäƤ��ޤ������������ˤ��i��ʼ���ȡ����������i�����褦�˚i��ʼ���
�����դ�һ�r�gĿ���Τ��ä�����
��ʼ�ޤä��Ф������ѧ�ڡ��r�g���ҙ���Ф�Ƥ��ʤ��i�ϡ�ǰ��i�����ˤ�Ԓ�����ͤƌ��ͤ롣
������������
�������������������֤ʤ����ʤ�����ѧ�ϵ���ʤ�����ɤʤ���
���Τ�����ǺΤ���֤Ȥ��Ƥ���Τ�ȫ���dζ�Οo�����ˤϡ����ꤻ���ˤ���������ǰ��i����ȥ��ν�핤ϡ��ޤ�������Ԥ���ꡢ�ٻ����֤�Ϣ�Ӥ����������ʤ����ĸ������å����ܤ����������˼�äơ����١���Ԓ�ʤɤ�����ɡ���Ϥ���ʚ�Dz���ϼ����ǰ�����Ǥ�����˼�äƘ��äƤ��ʤ��褦���䤿���Ӥ��Ƥ��롣����ˤ��v��餺���i�Ͻ��ˤ˾��x���ä����Ȥϟo���ä���
������ˤ��Ƥ⡢���ˤ�ͬ�����饹�ˤʤ��Ȥ�˼��ʤ��ä����ۤ顢Ѫ�������äƟo���Ƥ��ֵܤʤ櫓�������Ƥä��ꥯ�饹��֤�����Τ���˼�äƤ����ɡ�
���������֤ʤ���������ϵ�Υ�������x��������������C�M������ϵ�Υ������������
���ޡ������ʤ�����ɤͩ����
��1��Εr�ϥ�������ʤ��v�S�ʤ����̎�����������������֤������饹���ä��Τǡ��i�Ȥϥ��饹���x��Ƥ�������������2��ˤʤäƤ��顢��ѧ���Mѧ����ѧ�Ƅe�˥�����������ꡢ�������˥��饹�ɤ��������ޤ��ޡ�ͬ������������x��Ǥ��ޤä����ˤȚi�ϡ��Ҥ����Ҥ���ͬ�����饹�ˤʤä��Τ��ä���
�����饹�ˤϑT�줿����
���T�줿��Τ⡢ͬ�����饹��ū�Ȥ����뤷��
�����ä����ä������ˤäƤ������ޤ��ˤȴ��줢��ʤ��ä��Ԥ��������ؚݤʤ��������_�����ʤ�������Ҋ���롹
���S��������Ц�����Ȥ��Y���ˡ��ؤ˴̤���褦�ʤ��Ȥ��Ԥ��ơ����ˤ����ֹ�����귵�äƚi���Ҋ��ȡ��i�Ϥؤ�ؤ��Ц�äƽ��ˤ�Ҋ�Ƥ��롣���Ρ��ؤ�ؤ�Ȥ���Ц��o�Ԥ˸����������ˤ�Ĥ�����Τ��ä���
�������e�ˡ��㏊����ѧУ���ФäƤ������顢���_�ʤ���ͤ�������
���A�Υ��֥�ƥ��������㏊�������^�����Σ������ˤϡ�
�����ϡ��ƥ��Ȥ��λ����Ȥ��櫓�ˤϤ����ͤ�����衹
������ߡ������U�g�Ĥˤ�������Ƥ���櫓�ǤϤʤ��������ˤ�δ�����ش����Ȥ��Ƥ��Y���֤äƤ��롣�i�θ����ٻ餷�Ƥ��顢ĸ�ϥѩ���Ȥ�Ǥ�ơ����I���D�ˤʤä�����I���ۆT�Ƥ���i�θ����B�äƤ���o�Ϥϡ���ޤǡ�ĸ���P���Ƥ����o�Ϥκα�����ʮ�����B�äƤ��ơ�һ��Ϣ�Ӥ������褦���������ǤϤʤ��������顢�λ����Ȥ����ش����Ȥ��Ƥ��Y���ʧ�ä��Ȥ��Ƥ⡢����ҤȤ��Ƥ�ʹ�֤Ǥ�ΤǤ�ʤ����ष�����ش����Ȥ��Ƥ��Y���֤��A���뤳�Ȥ������ˤˤȤäƤ�ؓ���ˤʤäƤ���ΤǤϤʤ����ȡ�����������ۤɤ��ä�������ɡ����ˤϘS���������Ԥ�����ĸ�����~���ڤäơ�Ŀ�ˤߤ����ʤ�Τ����项�ȡ����ˤ�嶤�Τ��ä���
����ؤˡ������ʤäƤʤ�����
�����餫���褦�����������ơ����ˤϤ⤦һ�Ți��Ҋ����Я����Ƭ�֤�Ц�äƤ���i�ϡ����ߤ�Τ�o���褦��Ҋ���Ʊ����˸������ġ����ˤϤ��ޤꡢ�i�Τ��Ȥ�褯˼�äƤ��ʤ���
���ʤäƤͤ��衣����ˡ������㏊�褦���ʤˤ��褦����ǰ�ˤ��v�S�ʤ��������v��äƤ���ʤ衹
�����ˤ��ֵܤǤ��������֤������ʤ��ȡ���������ʤ櫓�Ǥ���
�����֤����Ȥ虜�Ȥ餷�����~�������ơ����ˤ�ü�g�˰���Ĥ������i���Ԥ�ͨ�ꡢ���ˤη����Q���դ��礤���ᡢ���ˤϚi���֤ˤʤ롣�礤���ԤäƤ⡢2���¤ۤɤ�������������2�����礤�����Ǥ��֤��������Ԥ���Τϡ������ݤ����ʤ������줬�i�����顢��Ӌ�ˤ���
�����Ϥ�ǰ��×�ߤ�����������ɤʡ������������ޥ����W�̤��뤫�顢�����Ȥ��Ф�����
�����������äƤ衣�����Ф��äƤС�
���i��ʼ����ˤ�������äơ��i���ߤ�ʼ���
�����ˤ����Ҥ˵��Ť����Τϡ����Υ۩����멡��बʼ�ޤ�10��ǰ���ä�����������Ը�Ƥ��ơ��s���Εr�g��10��ǰ�ˤϵ��Ť��Ƥ��ʤ��Țݤ��g�ޤʤ����ˤˤȤäơ����դε�У�r�g�Ϝ���Ǥ����Τ��ä����W�̥��ꥮ��ˤʤ뤫��˼��줿����ɡ����i�Τ褦���礯�i�����Τǡ��趨���⤫�ʤ��礯�Ť����Ȥ����������ޤ�ϯ�ϳ�ϯ����혤ʤΤǡ����ˤ�ǰ�ˤϚi�����뤳�ȤˤʤäƤ��뤬�����äѤ餫��Ů��ͽ��Ԓ��������졢У�T��ǰ�DŽe�줿�����ˤ�ϯ���Ť����Ȥ����O���顸���Ϥ褦�����Ԥ�������������
����֦�����Ϥ褦��
�����ˤ��O�����äƤ���Τϡ�ȥ��ͬ�����饹���ä���֦̫ꖤ���̫ꖤ⽡�ˤ�ͬ���褦���ش����ǡ��Ҥ�ؚ��������Ȥ������ɤǤ���ѧУ�ؤ�äƤ��������ξ������ƤƤ��뤻���������ˤ�̫ꖤȤ�롣�g�䤫���˵�����Τ����Ը�Ƥ��뤫�顢äƤ��������Ť��Ƥ��ޤ��Τ���
��5�¤ΰ�Фˡ����g������������Y��������ڤ��餷���衹
���ؤ��������ʤ����
������äơ��Y����ԣ��������ʡ����ĤǤ⡹
������ʤĤ��ϸ����ʤ��Τˡ��h���Ȥ��Ƥ��뤻���������Ĥ⽡�ˤϺ��¤ˤ���ԣ������褦��Ҋ���롣ѧУ�Υƥ��Ȥ��v���Ƥϡ��ژI���ܤ��ơ�����̶ȏ����Ƥ����кΤȤ��ʤ�Τǡ���ԣ���Ԥ�����ԣ����
������������������֦�⡢����ʤ˥��ꥮ�ꤸ��ʤ���������
�����ꥮ�ꤸ��ʤ����ɤ͡����Ēi����뤫�֤���ʤ����顭����
�����ˤ�ߡ��äơ�̫ꖤ��ش������������櫓�ˤϤ����ʤ��������顢ѧ��10λ���ڤ���뤳�Ȥ���횤ȤʤäƤ��롣�����֪��ʤ���⡢�X�ʤʤ��Ȥ��ԤäƤ��ޤä��ʤȡ����ˤ�˼�ä�����ɚݤˤϤ��ʤ��ä�������ʤ��Ȥ��Ԥä�̫ꖤΚݤ����Ƥ��ޤä��Ȥ��Ƥ⡢�ԤäƤ��ޤä��Τ�ȡ���������Ȥ������ʤ�������ˡ�����ʤ��Ȥǚݤ�����褦���ˤǤ�ʤ��ä���
���������줧���i���ޤ����Ƥͩ���Τ��詡���
��ǰ�����������ơ����ˤ�̫ꖤ���i��ϯ��Ŀ���Ƥ������i��ϯ���O�ˤϡ��i�����ˤǤ���ʯ�ӥ������äƤ��������ˤ�Ŀ���Ϥ��ʤ�ˡ������Ц�äơ��i�ϣ����Ƚ��ˤ��i�Τ��Ȥʤ�ΤǤ�֪�äƤ���褦�ˌ��ͤ롣���ˤϤ���ˌ����Ƥ⡢��������ҙ���Ƥ��ޤ���
����������У�T�ΤȤ�����Ů�Ӥ�Ԓ���������Ƥ����ɡ�
��֪��ʤ����ԤäƤ��ޤ��Кi��Ԓ�ʤɤ��ʤ��Ɯg��Τ������ֵܤ����Ԥ����Ȥ�ѧ��ΤۤȤ�ɤ�֪�äƤ��ơ�һ�w�˵�У���Ƥ��뤳�Ȥ�֪���Ƥ��롣�����顢���֤˥������¤��Ƥ⤹���˥Х�Ƥ��ޤ��Τǡ����ʤ��˱����Τ��Ȥ��ʤ���Ф����ʤ��Τ��ä���
���ޤ����衢�����ĩ���������ΥΩ�����J�����ޤ�ޤʤ����ʤ����礯�����äƤΡ�
���դ�褦�˅ۤ��ȡ�����Ͻ��ˤ�Ҋ�ơ������ʡ������ġ��Ȳ�ؑ�����褦�ˡ������餻�����i�ȥ����1��ΤȤ�����ͬ�����饹���ä����������H�Ѥ��J��Ϥ����餤�٤��褯���ЄӤϤۤȤ�ɹ��ˤ��Ƥ��롣��ϯ����혤���ϯ����������ǡ����ˤϤ��Ĥ���ˤλ�Ԓ����ˤ��Ƥ�����
����ǐ����ä��ʡ���ǡ�
�����礦�ɡ������Ԥ��K��ä��ᤰ�餤�ˡ����ᤫ��i�����������������˓B�ä�һ�Ť�����ȡ��֤�Я����֤ä��i�����C�Ӥ��������äƤ�����
�����äơ���ǰ�������ΥΩ���Ƚ��ѥ����褦�Ȥ��Ƥ��������������顢���ΥΩ���Ȥ�Ҋ�䤹������äƤ���Ϥʤ��
�������Ƥʤ������ǽ��ѥ��ä��Ԥ��ʤ衣�����ȷ����衣1�r�gĿ�νK���ޤǤˤϡ�
�������Ԥäƚi�Ͻ��ˤ��O��ͨ���^�����Է֤�ϯ�˥��Х���ä����O�������������Ƥ��른���Ҋ�ơ���Ц������
���K��äƤ�����ζ�ʤ������������������ϥ�����
��Ŀ��ǰ�����Ťߤ������Ԥ��Ϥ������ʤ��顢���ˤϥ��Х���Ф������R��ȡ����������e�Ρ�ҕ�����������Ԥ��櫓�ǤϤʤ����������������֤�Ҋ�y���������R���Ƥ���������ä����٤��ܤ䤱��ҕ�礬���t��Ҋ�����ݤ��������ޤ롣
���������������֤��ä��衣���㤡���
![(����ͬ��)[����]�ҵĸ�����ܹ�����](http://www.baxi2.com/cover/18/18983.jpg)