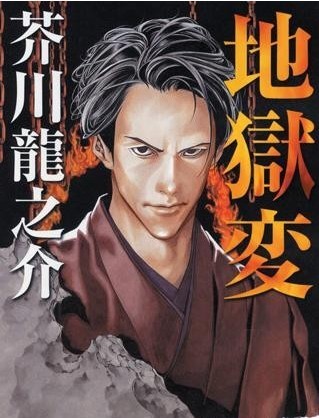�����(����)-��14����
�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������
��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���
������������
������ޤꡢ�o�����ʤ��ۤ��������衣���㡢�����L����äƤ��뤫�项
���i��Ŀ��Ϥ蘆���ˤ����Ԥ��Ȥ������A�Τ��Ϥ��ä��ФäƤ��ޤä����Τ��𤳤ä��Τ��֤��餺�����ˤϤ��Έ��������z����ޤޡ�����Ȥ�Ȥ��Ƥ�����妤줿��˱��������줿�����ǡ�����妤���䤿���Ϥ��ʤΤˡ��ѥ˥å���ꈤä��Ȥ���ͬ���褦�����������Ϥ��äƤ������夬��ʤäƤ�����
�������Ƥ��줿���ɤ��֤���ʤ����Ӥ������Ԥäơ�2�������Ͽڤ��������Ƥ��ʤ��ä����Ԥ��Τˡ����ʤ��ӤäƤ����Ϥ��ʤΤˡ�����ʤ��Ȥ�ƚݳ֤������Ȥ�˼��ʤ��Է֤θ���ˡ����ˤϑ���äƤ�����
������Ϛi�⡢ͬ�����ä���
���A�Τ��l���Ϥ��ꡢ���Ҥ�����ͬ�r�˴�Ϣ���¤��������꤬����ʼ��ơ��פ��Q�ꡢ���ˤ������äƤ���ΤǤϤʤ�����˼�ä����Ҥ����줿�褦���ߤ�����Ƥ������פä��𤨤Ƥ��뽡�ˤ�Ҋ���顢�ŤäƤ����ʤ��ä����ӤäƤ��ơ��Ҋ�����ʤ����ڤ����������ʤ���˼�äƤ����Τˡ��ɤ����Ʊ�������Ƥ��ޤä��Τ��Է֤��ЄӤ��֤���ʤ��ä���
�������Ρ����Ƥ�������ϡ�����
�����ݤ����ƾ��ơ���������Ƥ������֤�֤���ǰ����Ф줿����������ʤ���
�����ˤ�����ǰ����֤Τϡ�����ƤΤ��Ȥ��ä�������Ť��ʤ��ĄӤ��֤���褦�ˡ��i���Է֤��ؤ��դ꾆���
�褦�䤯����ߡ�������������Ť��Ƥ���핡�妤줿���˥�����驡����L�������꽡�ˤ����𤤤��������������줿�����Ǥ���ʤˤ�妤�Ƥ��ޤä��Τ����顢�i�Ϥ�ä�妤�Ƥ���������������ޤ�����˾Ӥ�Ȥ����꤬���äƤ��Ƥ��ޤä��Τ�������Ȥ⽡�ˤ������äƤ���Τ�֪�äơ��꤬���äƤ����ФäƤ����Τ��ɤ����Ϸ֤���ʤ�������ɡ����ɷ���Ԥä�嶤�Ƥ��줿����������ʤ��ä���
�����ΤޤޤǤ��Lа��Ҥ��Ƥ��ޤ���˼�������ˤ������Ϥ��ä������ݤ������Ȥ����A�Τν������Ф��ȡ��Ӥ���̤�ˤʤä����Х��ä���Ƥ���������ϼ����o���i�Τ�Τǡ�����ʤȤ����˷��ä��Ƥ��Ƥ�аħ�ʤ�������Ƭ�����褦�Ȥ��ơ���Ф����֤�ֹ�ޤ롣���֤�Ƭ��������ʤ����顢�i�ϙC�Ӥ��������������������ݤŤ��Ƥ��ޤä����ϡ����ä��Ƥ����Τ�ݤ������Ƥɤ�����Ф����Τ��֤���ʤ��ä���
���A�Τ��齵��Ƥ������������������ˤϤȤˤ������Έ���������ȥ�����ȥ��ե�����ؑ��롣�Ʃ���֥���Ϥ��ä��Ƥ����⥳����֤�ȡ�ꡢ�ƥ�Ӥ�Ĥ����������ͬ�r���餤������_�����������ơ���Ġ���w�����ͤ���
���ͤ������ˡ�
����ͨ��Ԓ��������졢���ˤ�������ɤ����¤������Τ��֤��餺������������Ȥ��Ǥ��ʤ��ä����i�Ϥޤ�����妤餷���ޤޡ����椨��֤ä����äƤ��롣�ݤ��ݤ��ȷ����դ�������Ƥ����~��ˮ���ˤʤäƤ�����
������룿���������p�äƤ�����ɡ�
���Ȥۤɤȉ���ʤ������ˡ����ˤϑ����ɤ����¤������Τ��֤���ʤ��ä�������ɡ�����Ƥ���Τ˟oҕ�뤳�ȤϤǤ��������ˤϿڤ��_������
������Ҫ��ʤ���ʤ��ä��Τ��衹
�����Ĥ�ͨ��Ԓ�������Ƥ��Ƥ��줿�i�ˤ���ʟo����ʤ��Ȥ��ԤäƤ��ޤ������ˤ���ڤ���������ʤ��Ȥ��Ԥ������ä��ΤǤϤʤ�������Ф���Ȥ�������ʤ����Ԥ������ä��Τˡ�˼���Ȥ��Y���˳��Ƥ������~���䤿����Τ��ä�������ǤϤޤ����٤�ꓐ��ˤʤäƤ��ޤ���˼�������ˤϸ�������
���o��������ˡ��i���٤�Ц�ä���
������äȤ�����؏��äƤ������͡����_�ΤȤ������ޤ���Ф��趨���o���ä������
����������
������ˤ���ʤӤ���̤�����_�ΤȤ����ˤ⤤���ʤ��������餵������ʤ����äƤ衣�礫��ʤ��ʳ�٤Ƥʤ������
�����ä��褦��Ц���i��Ҋ�ơ���Ӌ�˾ӤŤ餯�ʤä����Ҥɤ����Ȥ��Ԥä���ҙ�Ϥ��ꡢ�ޤ���ꓐ���״�B�ˤʤäƤ��ޤ��ȑ���Ƥ����Τˡ��i�Ϥ������Ȥ⤻������ꤷ�U�ʤ��������������ʱ����Ҋ�Ƥ����顢�ɤ�������ֱ�ˤʤ�ʤ��ä�����������ȡ���ڤФ��ꤷ�Ƥ�����
���������⡢�ޤ�ʳ�٤Ƥʤ����项
���ۤ��褦���Ԥ��ȡ��i�Ϥˤä���Ƚ��ˤ�Ц�ߤ����롣
�����������ʤ�������㤡�����礦�������͡�һ�w��ʳ�٤褦��
���ޤ���������ʤ��Ȥ��ԤäƤ���Ȥ�˼�鷺�����ˤφsȻ�Ȥ����ޤ��L�Έ��ؤ����i�����ˤ�Ҋ�ͤä����o���Ƥ��뤳�Ȥ˚ݤŤ��졢ͬ��Ǥ⤷�Ƥ���Τ����������i���Τ��Ƥ���Τ����äѤ�֤��餺��˼����·��ֹͣ���Ƥ��ޤ���ͬ�餵��Ƥ��Ҥ����ʤ���������˿������Ȥ�����ʤ���
�����ˤ��䤿���ʤä��Է֤������ࡣ��ݤˤ��餵�졢妤줿���Ϥɤ�ɤ����¤�Z�äƤ������i���Τ��Ƥ���Τ���������Ǥ��ʤ�����ɡ�״�r�����Ƥ��줿�Τ�Ҋ��ȡ��롣���Τޤ��������ơ��ޤ�ꓐ��ˤʤ�ʤ��ۤ���������������˼������Υɥ��Υ֤��֤�����
���������Ƥ衹
���Ȥۤɤޤǿ����Ƥ���˼���ˡ����ˤ��Ɇ�������״�r�����Ƥ���ơ�ϲ��Ǥ����Է֤��Ӥ롣ǰ�ޤǤ��v���ʤ��Ǥۤ������Ќg��������Ĥ�ʤ��褦���䤿���B�Ȥ�ȡ�äƤ���������ʤΤˡ���Ϥ������ϡ��٤������ʤ��褦��Ŭ��Ƥ��롣�i�α��Ĥ��������顢���ä��ꤷ���Τ��������������Ƥ��줿���顢�Ӥ��ǤϤʤ��ʤä��Τ�������������Ȥ⡢�e�θ�����Ƥ��ޤä��Τ���������������п�����ۤɡ��ɥĥܤˤϤޤäƤ��������ʚݤ����ƽ��ˤ�����_������һĿɢ���A�Τ��l���Ϥ��ꡢ���Ҥؤ��w���z�ࡣ������驡��������Ƥ��ʤ����ݤϥ�äȤ��Ƥ��ơ��ȤƤ��������ɡ��䤿���L��ɹ���졢�䤨����ˤϤȤƤ��ĵؤ褫�ä���
��������ΤϤ��褦��
�������Ƥ��Ƥ⥭�꤬�ʤ�����ä����ˤϡ��������ϡ��i�Τ��Ȥ���ΤϤ�ᡢ妤줿�����Ѥ�����һ�ˤǐ����ȿ����Ƥ��Ƥ⡢��ζ���o�����ȤϷ֤��äƤ������⤷�������顢���դˤʤ�С��i�ΑB�Ȥ�ǰ��ͬ���褦�ˤʤäƤ��뤫�⤷��ʤ�������˼�äơ����ˤϤ�����˼�����жϤ�����
���������椨��妤줿�������ǥ�ӥ˽��ꡢϴ媻���Ф˷���ͻ���z��Ǥ��齡�ˤϥ��å�������ä�������1�L�g���ޤȤ��ʳ�¤������趨�ϟo�������i����Ф���郎��äƤ��ʤ��ä��������Ԥäơ����I������Ф��Τ⡢�������Τˏ����ФäƤ���褦���Ӥ��ä������i����Фˤϡ�ţ�⤬��äƤ��롣Ұ���Ҥ��_���Ƥˤ���äƤ���Τ�Ҋ�ơ����ˤ��⤸�㤬�����뤳�Ȥˤ������⤸�㤬�Ϥ���ʤ˕r�g��������ʤ��������Ϥ⤢�꤭����ʤ�Τ��त��ĸ������Ȥ��Ƥ��������ǡ��褯ʳ�ˤ���Ƥ��뤬���ݤˤ��Ƥ�����ԣ�ϟo���ä���
�����ޤͤ��Ȥˤ��㥬�����Ƥ������ƴ��Ф롣�ե饤�ѥ���ͤ�������ţ���롣����̶ȡ���ͨ�äƤ�����ˮ�����ơ�ţ�⤫������֭��ȡ�äƤ���ˤ��Ͷ�뤹�롣���줫�饸�㥬����Ȥ��ޤͤ������Ƥ��顢�ơ��ߤ��ɰ�ǡ����礦�������ζ��գ����롣һ�B�����I�����Z��Ƥ��ơ�������������Ŀ�ˤ���ΤϾä��֤���ä�����Ҫ�I�褯�����������z��Ǥ����g��ζ��֭���������ȡ�Ƭ��偤��֤���Ф����l���ä����Τ��֤���ʤ�����Ƭ��偤����һ���Ϥ��ä���Ƥ��ƽ��ˤ��֤Ͻ줫�ʤ�������Ǥ�̨��ʹ�äƤȤꤿ���ʤ����ˤϡ�����Ӥ롣
���������á�
������һ�i�ǽ줭���������Ԥ��Τˡ����β���С��s�ޤ�ʤ������Į���֤������Ѻ���褦����Ф�����ָ�Ȥ�ȡ�äƤ��Ȥ˽줯������ȡ���֤����ʤ����B��褦�Ȥ����Ȥ��ˡ���������֤���ӤƤ���偤�ȡ���֤�������
�����죿��
��������������Ƭ��偤�֤ä��i�����äƤ��������x�Ͻ������g���ˤ������Ȥ��@�������Ʒ��꤬�����ʤ��ä����i���^�˥������Ƥ��ơ�ǰ���٤�ˮ���ΤäƤ�����ˮ��Τ������Ф��Ԥ��Τϡ������Ԥ����Ȥ��Ԥ��Τ���������Ҋ��ߡ����ʤ��Ȥ��Ƥ��ޤä���
���i�ϺΤ��Ԥ�ʤ����ˤ�偤�ͻ�������������졢ʹ����Ǥ��硹���Ԥ����ܤ�ȡ�똔�˴ߴ٤롣�o�Ԥ��ܤ�ȡ�ä����ˤ�Ҋ�ơ�ҕ������������ե饤�ѥ���Ф���äƤ���ߤ�Ҋ�Ĥ�ơ����դ�ϦƤ롣
�����դ�Ұ�˳����
����Τ�Ҋ�¤��⤷���i��Ҋ�ơ����ˤ�Ϣ���¤����������ɤ���ɤ�Ҋ���顢���줬Ұ�˳���ˤʤ�Τ��̤��Ƥۤ������餤�������줿�褦�ˡ������⤸�㤬���衹���Ԥ��ȡ��i�ϡ������ޤ��gߡ��������ȿ�Ц��������
�����Ӥ��������⤸�㤬����ζ������͡�
�������Ǥ⡢�ʤ����ʤ���ĸ������⤸�㤬�ϡ�
�����ˤ�偤�ˮ�����ʤ��顢���줿���Ȥϴ𤨤褦��˼�������¤Ƥ�����ĸ�������⤸�㤬�ϥޥ����櫓�ǤϤʤ��������Ĥ�Τ������ʤ���˼�äƤ������Κݤʤ������Ԥ��ȡ��i�ϡ������Ȥ����⤸�㤬�äƤɤ��ζ����������������С�����Ԥä������줬���Ȥ�ʤ��ä����ˤϚi���Ҋ�����������������Ǥ��ʤ��ä����ե饤�ѥ��Ҋ�Ĥ��Ŀ�ϡ��٤��������������ǡ�����ƤϤ����ʤ����ԤäƤ���褦���ä���
��ζ��֭�ϺΤˤ���Σ����ց����뤳�Ȥ���ʤ顢�ց������ɡ�
�����㤡���Ʃ���֥��ä������������ơ�
���֤��ä���
���Ȥۤɤα���������ʤ��m��Ҋ�����ˡ��i��Ц���ʤ��饭�å��������Фä���������L�ˡ���Ȼ��Ԓ���������դ�����ʤ�ơ�˼���⤷�ʤ��ä������줬��ͨ�ʤ�����������ɤ���ݤˤʤäƤ��ޤ������֤����~�������ʤ������դޤǤ�ꓐ����ä��Τˡ�����ʤ��Ȥ����ä������Ǥ�������äƤ��ޤ��Τ�������������⤳��⡢�i��Ԓ�������Ƥ��뤫�顢���ˤϴ𤨤Ƥ�����������i���ФǺΤ��仯�����ä��Τ����������Ʃ���֥���ä��Ƥ���i���٤�Ҋ�Ĥ�ơ����ˤ�Ŀ���ݤ餷����
���i���������ä��櫓�ǤϤʤ�������������Ƥ��顢���ˤ��٤����ġ����äƤ�����
�����㥬����˻�ͨ�äƤ���Τ�_�J���Ƥ��顢���ˤ�ζҊ�����Է֤����ä��⤸�㤬��ʳ�٤Ƥ���ȡ���Ϥ�ĸ���⤸�㤬�ϺΤ������ʤ��褦�ʚݤ����Ƥ��ޤ�ʤ��ä������äƤ���Ȥ������O��Ҋ�Ƥ��뤬��ȫ�Ƥ�Ҋ�Ƥ���櫓�ǤϤʤ����Τ����������Ƥ���Τ������������������ʤɤ��Ƥ��ʤ��ä�ĸ�Τ��Ȥ����顢���귽�ʤ������Ƥ��ޤäƤ��롣���θ�ˡ����ˤ����Ԥ������Ȥ��ʤ�������Ϥ����ĸ�餷���ȡ����ˤ�˼�äƤ�����
������⤸�㤬��褽�äơ�������ζ��֭�����Ƥ��������Ǥ˲���ˤϤ���褽�äƤ��äơ��i���Ʃ���֥��ߤ�Ǥ��롣���դ�Ϧ��⤸�㤬�ȥ��������ζ��֭�ξߤϡ���䤷�Ȥ狼�����Ǭ��狼����ä��Τǡ������ˮ�˽����Ƒ������e�������˽g�ä��Ƥ��Ƥ�����һ�Ĥޤ߷֡��狼������Ǥ������Ф����롣����٤������줼�Ƥ��顢ζ��֭��Ʃ���֥�K�٤���
���i�Ϥ��Ǥ�ϯ�˸����Ƥ��ƥƥ�Ӥ�Ҋ�Ƥ��������ˤ��֤ä������Τ����ǸФ���ȡ�Ŀ��ǰ���ä��줿ζ��֭��Ҋ�Ĥ�ơ��狼��Ȥ�䤷�����Ƚ��ˤ˴_�J������
��������
���ؤ�����䤷��ζ��֭�Ȥ������Ҋ����
������ĸ�������Ƥʤ��ä��ä���
����䤷�Κn���������ä��ǽ��ˤ�������䤷�Τߤ�֭�����äƤ������ٻ餷�Ƥ����ĸ�����똔�ˤʤä������ǡ����ޤ�ڤˤ��ʤ��ʤä��������줬���Ĥ�����ä��Τ���ҙ���Ƥ��ʤ���ζ��֭���äơ�����ǰ��ҹ���ä��֤�����ä��Τ����ց����뤳�Ȥ϶ࡩ���뤱��ɡ�ζ�����Ϥ��٤�ĸ�����Ƥ���������ǰ�Ϥ��ޤ��ޡ��֤��դ��Ƥʤ��������ä����齡�ˤ�ζ�������������ä���
�����äƟo���ä���˼�����ɡ�����ʳ�٤褦�衣���롹
����Ԓ���жϤ�����褦�˚i��������������ˤϤޤ����å�����ä��÷Ť��ˤ��Ƥ����⤸�㤬�ȥ������֤äơ������˥Ʃ���֥�ؤȑ��롣���Ĥ⡢ĸ�ȸ�����������äƤ��ơ����ˤȚi���Oͬʿ�������ˤ��Ӥʤ��������ƶ��ˁK��������Ҫ������Τ��������ȿ����Ƥ��ޤ����㤬ֹ�ޤä������Ύڤ���ӥ��С����ˤ��O�ˁK�������Τ�����˸Ф��롣����˼�äƤ��ޤä��顢�Ӥ����Ȥ��������ˡ����Έ�����������������
���������ˣ���ʳ�٤ʤ��Σ���
��������������������
������ʽ��ˤ�Ӡ������i������Ӡ��Ŀ��Ԓ�������Ƥ�������Ȳ���Ϥ��Ĥ��ϯ�ˁK�٤��Ƥ��롣�����Ǥ⤷�����ˤ��i�Ό���ˤʤ�����С�������R�Ƥ��뤳�Ȥ˚ݸ�����롣����ʤ��ȤƤ��ޤ��С�ͬ�����Ȥ��R�귵���Θ��ʚݤ����ơ����ˤ����Ʃ���֥���ä��Ți���O�����ä���
�����O�ˤ���i�ϡ���ӥΰ¤ˤ���ƥ�Ӥ�Ҋ�Ĥ�Ƥ��������M�϶��ȡ����д���ؼ����äƤ��ơ������ߤ�����ü�g�˰���Ĥ��ʤ���ӳ�������줿д���Ҋ�Ƥ���������ʤ�Τ�ȫ
![(����ͬ��)[����]�ҵĸ�����ܹ�����](http://www.baxi2.com/cover/18/18983.jpg)